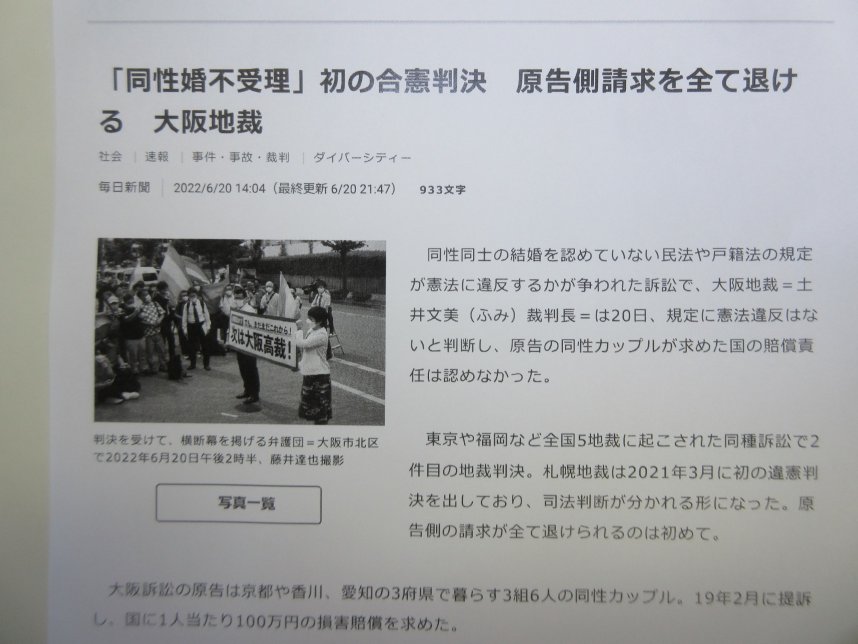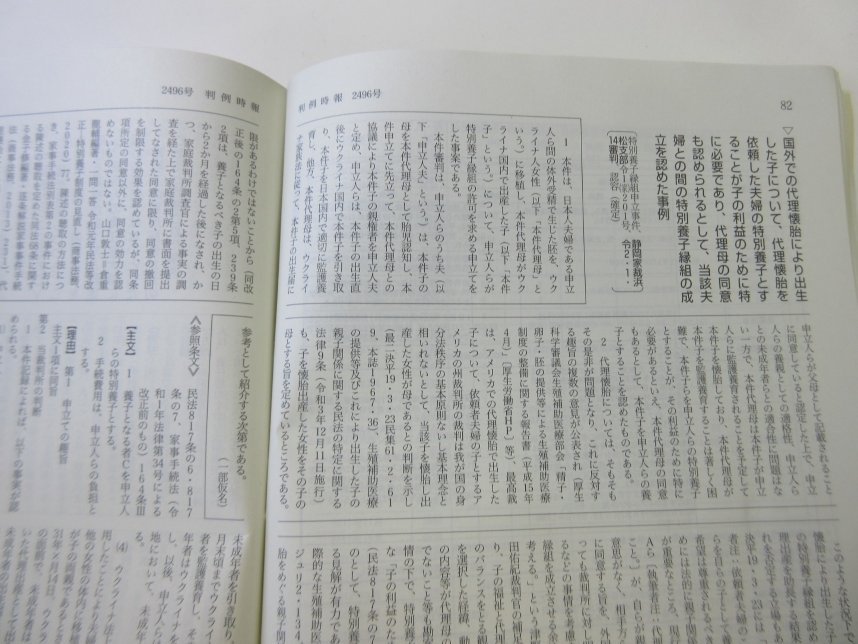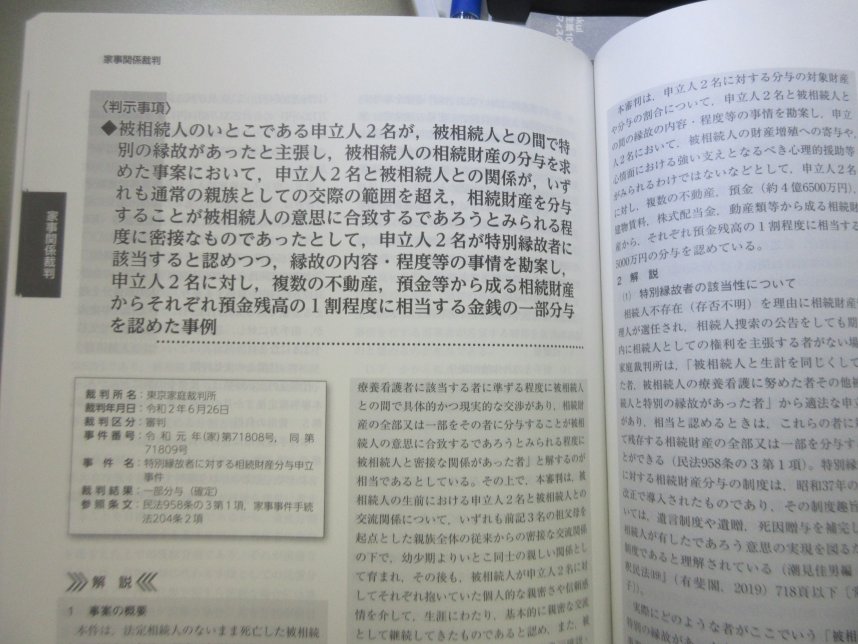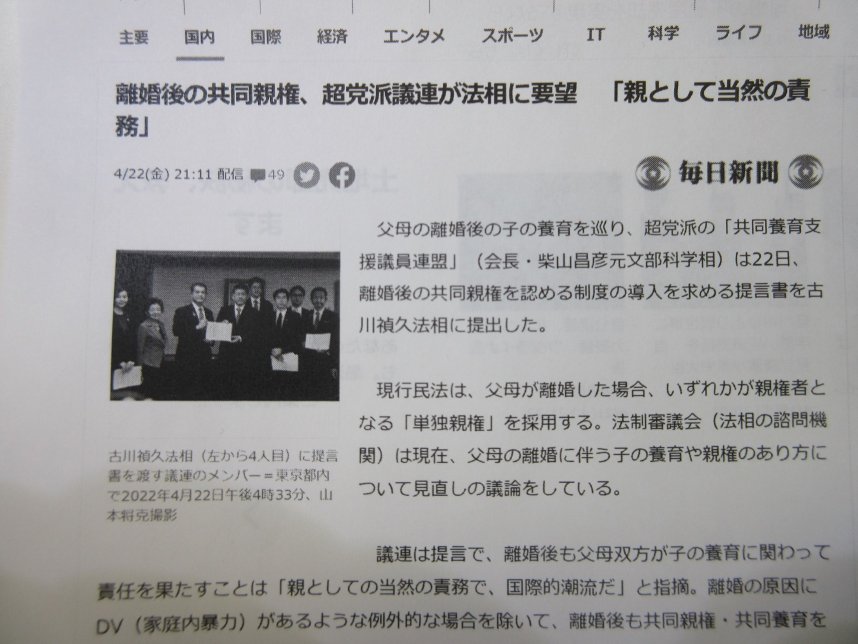同性婚
今月20日に大阪地裁が、同性婚を法律で認めていないのは憲法違反であるとし、その立法不作為により損害を受けたとして国家賠償を求めた裁判で大阪地裁は同性婚を認めないのは憲法に違反しないという内容の判決を言い渡しました。現在の日本の法律上の婚姻制度は異性間のみです。ただ、近年価値観の多様化やLGBTといった少数派の権利がいわれるようになり、これまで当たり前と思ってきた婚姻制度にも変化の兆しが見られます。すでに法律上の婚姻ではありませんが、自治体レベルでは異性間でパートナーシップという婚姻類似の制度を認めているところもあります。もっとも、あくまで当該自治体限りで別の自治体に住所を移転すれば、制度は使えませんし、そもそも法律上の婚姻ではないので、相続も発生せず、配偶者控除などもありません。諸外国では、国の制度として、同性婚やパートナーシップを認めている国もかなりの数あります。ヨーロッパ、北米、南米の国が多いようですが、アジアでも台湾は認めているようです。日本でも、昨年札幌地裁が今回の大阪地裁とは違う内容の判決を出しました。たしかに、今は同性婚を認めないのが憲法違反かといわれると判決がいうように法の下の平等にも婚姻の自由にも反しないように思います。この問題は結局立法による対応が必要かもしれませんが、それでは同性婚容認派が多数派にならない限り法律の改正は望めません。とりわけ、この判決の婚姻が「男女が子を産み育てる関係を社会が保護する目的」とする価値観はあまりに保守的です。子の関係でいえば養子縁組などの制度も存在します。それに子を育てるだけが婚姻の目的とは思えません。さらに価値観の多様化が進んでくれば、数年後には立法不作為が違憲とされるのかもしれません。